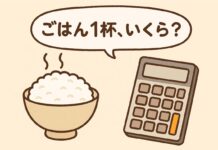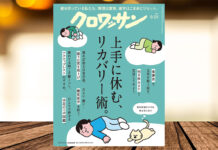YouTubeのおすすめに「日本とアメリカ、夏休みの宿題の比較」の動画が表示されていたので、なんとなくクリックしたらすごく面白い! 今回はその動画をご紹介します。
その前に、わが家には小学1年生の息子がいます。
初めての夏休みを迎え、ドリル、絵日記、読書感想文、朝顔の観察日記など、毎日コツコツとこなさないと終わらないほどの宿題が渡されました。
大変だけど親子で頑張らないといけないな……と思っていました。
しかし、アメリカの小学校は衝撃的な宿題の少なさだったのです。
アメリカの夏休み、日本の2倍の長さで宿題も少ない!?楽しそうすぎるんだが
その動画は、こちら!
チャンネル名は「Kevin’s English Room / 掛山ケビ志郎」。男性3人組の番組で、アメリカ生まれ・アメリカ育ちの日系アメリカ人・ケビンさんが、アメリカの宿題事情を語ってくださっています。
ケビンさんのご両親は日本人で、高校生の半過程までアメリカで過ごし、現在は日本で暮らしているとのこと。
以下、動画のポイントをかいつまんでご紹介します。
小学5年生・6年生の間の夏休み、宿題全6ページだった
実際、宿題はどれくらいの分量だったのか。
小学5年生から6年生にあがるときの夏休みの宿題は、ページ数が6ページほどで終わり。それに全教科(英語・文学、算数、歴史、地理など)が入っていたそうです。
アメリカの小学校、夏休みの日数は11週間(2か月半)
「アメリカの小学校の宿題が少ないってことは、夏休みの日数が少ないんじゃいの?」
そう思う方もいるでしょう。
しかし、アメリカの小学校の夏休みは、日本の約2倍!
10週間から11週間が一般的だそうです。約2ヶ月半。
ケビンさんが通っていたアメリカ南部の小学校では、「5月末から8月上旬」くらいが夏休み期間だったとのこと。
アメリカの小学校は、子ども達に勉強させないの?
アメリカの小学校では、夏休みを以下のようなスタンスで捉えているそうです。
夏休みは……
- 家族と一緒に過ごしてほしい
- 自分の趣味や楽しみを見つけてほしい
- 学校から解放されてリラックスするために過ごしてほしい
また、たった6ページほどしかない宿題には、「School Brain(学校の脳)を無くさないためにも、何問かの宿題をやってくださいね」と書かれているとのこと。
何して過ごす? サマーキャンプへ行くのがメジャー

では、子ども達は長〜い夏休みを、一体どのようにして過ごすのでしょうか?
サマーキャンプへ参加するのが一般的だそうです。
そこでは、ハイキングへ行ったり、キャンプをしたり、カヌーで川をくだったりし、子ども達が集まってサバイバルスキルを身につけるとのこと。
ただし最近は、「音楽をやりましょう」「プログラミングを学びましょう」「マジックを習得してみよう」「言語を学んでみよう」「サッカーを習おう」など、過ごし方に多様性広がっています。
これらは学校は関係なくて、他の団体が主催しているそうです。
期間は、2〜3日から1〜2週間で、短期集中型の体験になります。日本でいうところの、水泳の夏期講習のようなものかもしれませんね。
とにかく、子ども達は自分の好きなことを、夏休みのあいだに経験します。
ちなみにケビンさんは、やりたくなかったのでサマーキャンプなどには参加しなかったとのことです。
アメリカ人は、家族と過ごす時間を大切にしている

最後に総括として、ケビンさんは「アメリカではファミリータイム(家族と過ごす時間)をとても重要視していると感じる」とおっしゃっていました。
同チャンネルには、こんな動画もあります。
ファミリータイムが重視されている様子がわかるでしょう。ぜひ、合わせてご覧ください。
40秒のショート動画です。
■関連リンク

【追記】ドイツの夏休みも宿題無し、習い事もお休み

本記事公開後、Facebook「パパやる」ページにドイツ在住のNaomi Rickertさんよりコメントをいただきました。ありがとうございます!
ドイツの娘たちが通う学校は夏休みは6週間ありますが、宿題はないですよー。夏休みだけでなく、長いお休みは宿題もないし、学校だけじゃなくて普段の放課後の習い事なんかも全部お休みになります。大人だけじゃなくて子供にも休みは必要だから、しっかり休めということみたいです。羨ましいですね。
補足として、こんな情報もいただきました。
長期休暇中は普段の習い事がなくなるので、地域ごとに子供向けの色んな体験教室とかアクティビティがあったんですが(うちの地域では郵便でパンフレットが子供あてに送られてきます)、コロナの影響で去年から全くなかったり、ほんの少しだけ屋外限定であったり、子供も可哀想です。
日本の小学校のやり方は、世界から見たら非常識なのかもしれませんね。
勉強とは? 学習とは? 学力とは? ……色々考えさせられるきっかけになりました。